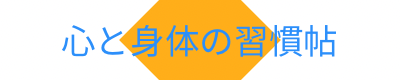「なぜ続けられないと感じてしまうのか」
「やると決めたのに続けられない」
失敗すると、「意志が弱いせいだ」と自分を責めてはいませんか?
はたして本当に意思のせいでしょうか?
私たちの “続けられない” の背景には、
気持ちだけではどうにもならない理由があります。
それは、 “脳が変化を嫌がるから” なんです。
実は習慣化が難しいのは、あなたの性格や気合いの問題ではありません。
脳は、もともとそういう仕組みになっているだけなんです。
ここでは、なぜ脳が新しい習慣に抵抗を感じるのかを、
「ホメオスタシス(恒常性)」と「予測脳」
という2つの観点から解説していきます。
仕組みを知ることで、「自分を責めなくていい理由」がきっと見えてくるはずです。
脳は変化を避けたがる(ホメオスタシスの影響)
私たちの身体には「ホメオスタシス(恒常性)」という仕組みがあります。一つは体温や血圧などを一定に保つ身体的な恒常性。
もう一つは、心や行動に作用する心理的な恒常性です。
この心理的な恒常性によって、
私たちは新しいことを始めようとすると、
無意識に「いつも通りを保ちたい」と思ってしまいます。
たとえば、何かを始めようとした時に、
「今日はちょっと疲れてるし...」
「また明日からでいいかな...」
と感じたことはありませんか?
これは意志が弱いからではなく、
脳が “いつも通りでいよう” とブレーキをかけている自然な反応なんです。
習慣を変えるというのは、
このブレーキの存在を理解した上で、
少しずつ “自分のパターン” を変えていく作業でもあります。
だからこそ、最初はうまくいかなくて当然。
それはあなたの意思の問題ではなく、
人間の脳の仕組みによるものなのです。
脳は予測できる行動を好む(エネルギー節約の仕組み)
私たちの脳は、予測できる行動や環境を好みます。
これは「予測脳」とも呼ばれる考え方で、
脳はできる限りエネルギーを節約しようとするため、
「すでに知っている・慣れている行動」に安心を感じるのです。
新しいことを始めるとき、なぜか疲れやすかったり、
理由もないのに「やめたくなる」ことがあります。
それは、脳にとって“未知”や“変化”は処理するのにエネルギーがかかるから。
知らない道を歩くときにちょっと緊張するように、
習慣を変えることも、脳にとっては「警戒すべきこと」になるのです。
つまり、やらない理由が自然に浮かぶのは、脳が自分を守っている証拠。
これは「意志が弱い」のではなく、脳が賢く働いているからとも言えます。
この仕組みを知っておくと、
「自分って本当にダメだな」と感じたときも、
少しだけ優しい目で自分を見られるようになるかもしれません。
環境・感情・思考の“見えないハードル”
「習慣化が続かない理由」として、
意志や脳の仕組みだけでなく、
環境・感情・思考の条件も大きく関わっています。
たとえば――
- 帰宅が遅くなって疲れていた(環境)
- 落ち込んでいて、やる気が出なかった(感情)
- 「こんな短時間じゃ意味ない」と思ってしまった(思考)
どれも一見ささいに思えるかもしれませんが、
これらが重なると、習慣の行動を大きく左右してしまうことがあります。
この “見えないハードル” のやっかいなところは、
本人の努力ではコントロールしきれないことも多いという点です。
それでも私たちは、「できなかった自分」を責めがちです。
だからこそ大切なのは、
「できなかったのは自分の弱さではなく、状況だったのかもしれない」
と、視点を変えてみること。
思い通りにいかなかった日も、
「今日は動けなくても仕方なかった」と気づければ、
自分を責めずにすみます。
さらに、そこから対策を考えることもできる。
それが習慣化の新たな第一歩になるかもしれません。
よくある習慣化の“落とし穴”
習慣化しようとするとき、多くの人が“つまづくパターン”があります。
それは意志の問題でも、やる気のせいでもありません。
実は、よくある「思い込み」や「無意識のクセ」が、
私たちの習慣化をそっと邪魔していることが、とても多いのです。
たとえば――
- 最初から完璧にやろうとしてしまう
- 少しできなかっただけで「意味がない」と思ってしまう
- モチベーションがない日は、何もできない気がしてしまう
これらは、誰にでも起こりうる “習慣化の落とし穴”
ここでは、そうした典型的なつまずきを3つ紹介しながら、
その背景にあるしくみと、どう乗り越えたらよいのかを一緒に考えていきましょう。
最初から頑張りすぎて疲れる(脳内の報酬系・ドーパミンの作用)
習慣を始めるとき、気合いを入れて
「よし、毎日やるぞ!」と高い目標を掲げたことはありませんか?
実はこれ、挫折の第一歩になりやすいんです。
私たちの脳には「報酬系」と呼ばれる機能があります。
これは、行動の結果として得られる “ごほうび” (達成感や満足感)を期待して、
ドーパミンという神経伝達物質が分泌されることで、やる気や快感を感じるというものです。
ところが、最初に大きな目標(成果や快感)を求めすぎると、
脳にとってそれが “基準” になってしまい、少しの変化では満足できなくなってしまいます。
その結果――
「昨日より少し良かった」では物足りなくなり、
「今日はあまりできなかった」→「もう意味ない」
と、極端な判断に陥ってしまう。
これが、「頑張りすぎた結果、燃え尽きてしまう」よくあるパターンです。
だからこそ、最初は “ちょっと物足りないくらい” でOK。
「今日は軽くできたな」くらいの感覚の方が、
長期的にみると「できた」状態を長く保ちやすくなるのです。
できなかった日=ゼロと思ってしまう(All or Nothing思考)
習慣化がうまくいかない理由のひとつに、
「全部できなきゃ意味がない」という極端な考え方があります。
これは「All or Nothing思考(全か無か思考)」とも呼ばれ、
「白黒思考」として耳にしたことがある方もいるかもしれません。
特に、完璧を求めやすい人ほど、こうした思考に陥りがちです。
たとえば――
- 毎日10分運動しようと決めたのに、5分しかできなかった
- 1週間続けられたけど、8日目にやらなかった
- たった1回スキップしただけで「もう続かない」と感じてしまう
こんな経験、誰にでもあると思います。
でも「白黒思考」になっていると、
- 「5分しかできなかったら意味がない」
- 「1日やらなかったら今までの努力は水の泡」
- 「1回休んだら、もう全てが無駄」
と考えてしまいがちです。
–––本当にそうでしょうか?
実際は、あなたが積み重ねてきたことは決して無駄ではありません。
たとえ少しだったとしても、「できた」という事実は確かにそこにあるのです。
むしろ大切なのは、
「できていたという事実」と、
「できなかったことを受け止めて、また戻ろうとしているあなた自身」――
それこそが、習慣を作ろうとしている何よりの証拠です。
習慣化に本当に必要なのは、
「毎日完璧にこなすこと」ではなく、
「できなかった日があっても、また戻れること」。
だからこそ、続かなかった日を “失敗” と捉えるのではなく、
「戻ろうとする自分」や、「戻ってこれた自分」にこそ目を向けてあげてください。
モチベーション依存の限界(自律神経とエネルギー)は
習慣化を始めたとき、つい「やる気が出たらやろう」と思ってしまいがちです。
でも実は、この「モチベーション頼り」こそが、習慣が続かない大きな原因になることがあります。
私たちのやる気や気分は、ストレスや睡眠不足、環境の変化などに大きく左右されます。
これらは自律神経系に影響を与え、メンタルの不安定さにつながることも少なくありません。
生活習慣が乱れると、交感神経と副交感神経のバランスも崩れ、
その結果、
「なんとなくやる気が出ない」
「今日はいまいち動けない」
という日が出てくるのです。
つまり、モチベーションとは生活状況に左右される非常に不安定なもの。
それに頼り続けていると、習慣化するのが難しくなってしまいます。
だからこそ必要なのが、 “やる気がなくてもできる仕組み” です。
- 時間や場所をあらかじめ決めておく
- 行動のハードルを極限まで下げておく
- “できた”と感じられる目標を小さく設定しておく
こうした工夫は、モチベーションが低い日でも
自分を動かす“きっかけ”をつくってくれます。
習慣とは、やる気がある日に頑張るものではなく、
やる気がない日でも “できる”
できなくても “また再開できる”
そんな形が理想なのです。
続けるには「失敗する前提」で設計する
これまで「続かない経験」をした人ほど、
「今度こそ続けたい」
「今度は絶対に失敗したくない」
という気持ちが強くなりがちです。
でも、習慣化において本当に大切なのは、
「失敗しないこと」ではなく、
「失敗してもまた戻れること」です。
私たちの生活には波があります。
気分が落ち込む日もあれば、体調がすぐれない日もある。
忙しくて、予定通りにいかない日も、きっとあるはずです。
だからこそ、習慣を続けるためには――
最初から「うまくいかない日がある前提」でいることが大切です。
- 毎日続かなくても、「できた日」を積み重ねていけばいい
- 完璧じゃなくていい。「できた」に戻れたなら、それでOK
- 中断しても、「また始められた自分」を認めてあげてください
こうした心構えができると、
一度の中断や失敗に振り回されることなく、
長く、柔軟に、続けていけるようになります。
習慣で大切なのは、「ずっと続いていること」ではなく、
中断しても、何度でも戻れることなのです。
失敗する前提で考える
習慣を続けるには、「失敗しないための努力」よりも、
「失敗することを前提にしておく」ことが大切です。
ここでいう失敗とは、あくまで
「一時的にできなかった」時のこと。
それ自体は全然問題ありません。
ただ、「できなかったから、もう意味がない」と思ってしまうとマズい。
その思考が習慣を断ち切ってしまう原因になります。
「今日は無理だったけど、また明日から頑張ろう」
「中断してたけど、再開できた自分偉い!」
こんな感じで、出来なかったことを見るより
戻って来れた自分を肯定する方が、習慣として続けていきます。
大切なのは、うまくいかない日があることを前提にして、
その時に備えた “戻るルート” を作っておくこと。
たとえば――
- 毎日やるのが難しければ、「週に◯回できたらOK」にしておく
- スキップしたら、休養日として、翌日から再開する
- 「また始められたら、それはOK」
こうして、失敗を想定し、ハードルを下げておくことで、
習慣はぐっと続きやすくなります。
完璧じゃない習慣の方が長続きする理由(成功率の脳内処理)
「どうせやるなら完璧に」
そんなふうに考えてしまう人は、きっと真面目で、努力家で、理想が高い人です。
でも、習慣化においては、完璧を目指すことが足枷になってしまうこともあります。
私たちの脳は、「成功した」「できた」と感じたときに、
ドーパミンという“快の感覚”をもたらす物質を分泌します。
この「できた感覚」があるからこそ、「またやろう」と思えるようになるのです。
ところが、完璧を基準にしてしまうと、
少ししかできなかった日は「失敗」と認識されやすくなります。
そうすると、ドーパミンの分泌量も少なく、脳にとっての報酬が小さくなるため、
「やっても意味がない」という印象が残ってしまうのです。
だからこそ大切なのは、 “できた” と感じる目標を小さく設定しておくこと。
たとえば――
- 5分のストレッチができたらOK
- 忘れた日は「気づいたときに1回だけやる」でOK
- 思い出せただけでも、習慣に意識が向いているからOK
こうした “ゆるめの合格ライン” の方が、
結果的に「できた」が増え、ドーパミンの分泌が促されることで、
習慣として根づきやすくなっていきます。
習慣化は、毎日100点を目指すゲームではありません。
どちらかといえば、
『目指したい自分に向かって、毎日1点ずつ貯めていく作業ゲーム』
そんなイメージが近いかもしれません。
「塵も積もれば山となる」なんて言いますが、正にそれです。
「できた自分」を少しずつ積み重ねて、
気がついた頃に理想に近づいている。
それが、習慣だと思います。
……まあ、気が遠くなっちゃいますけどね。
継続より「復帰のルート」をつくる
習慣をつくるとき、「継続すること」が目標になってきますよね。
もちろん、続けられたら素晴らしいことです。
でも本当に大切なのは、「継続」よりも「復帰できること」――
つまり、 “うまくいかない日があっても、また戻ってこれる状態” をつくることなんです。
どれだけ完璧に続けていたとしても、
人生には予測できない出来事や、気分の波、体調の変化があります。
どこかのタイミングで必ず「続けられない日」はやってきます。
その時に、「もうダメだ」とやめてしまうか、
「また戻ってこれたからOK」と思えるか。
そこが習慣として定着するかどうかの、大きな分かれ道になります。
だからこそ、「続けること」よりも、
「できなかった自分を許せる余裕」
を心の中に持っておくことが大切です。
私自身も、筋トレを習慣にしていてノートに記録をつけています。
でも体調が悪いときや仕事で余裕がないときは休むし、もちろんノートも書きません。
再開する時も、いきなり全開だと身体がもたないので、
まずは散歩やストレッチから始めたり、数日は決まったメニューの半分だけやる。
これが自分なりの “復帰のルート” なんです。
「今日はこれくらいでいい」
「また動き出せた自分、えらいな」
そんなふうに、戻れたことを自分で認めてあげることが、習慣を長く続けるポイントです。
習慣とは、止まらずに続いている一直線の道ではありません。
途中で止まったり、曲がったりしながらも、
また歩き出せることができる “復帰のルート” があることのほうが、
ずっと大切なのです。
まとめ 〜失敗は“習慣の一部”として認めていい〜
習慣化というと、
「毎日続けること」
「サボらないこと」
が大切だと思われがちです。
でも、この記事をここまで読んでくれたあなたなら、もう分かっているかもしれません。
本当に大切なのは、
「続けること」よりも「戻ってこれること」。
「失敗しないこと」ではなく、「失敗しても自分を責めずにいること」
なんです。
続かない日があっても大丈夫。
思うようにいかない日があっても大丈夫。
習慣は、そういう日も含めて、あなたと一緒に形を変えながら育っていくものです。
完璧を目指す必要はありません。
「昨日よりちょっとできた」
「また戻ってこれた」
そんな小さな成功体験こそが、習慣をつくる一歩になります。
失敗は、習慣化の敵じゃありません。
むしろ、習慣化の一部として “許されていいもの” なんです。
なんなら今の失敗が次の成功のキッカケになる。
考え方一つで色々変わります。
あなたがこれから作っていく習慣が、
人生を豊かにするものになりますように。